ブログタイトルでも触れておりますが、私の息子は自閉症です。時間を経るごとに彼の中での成長(理解や世界の解像度が上がるなど)は感じられるものの、3歳を過ぎても2語文が出てこず、定型発達のお子さんに比べてやはり遅れは大きいと感じます。
そんな中でタイトルの本に出会い、妻と私は衝撃を受けました。正確には本書を映像した作品に出会い、次に書籍に当たり、双方に深い感銘と衝撃を受けたのです。
言葉を発せない自閉症児の内面。心の内に隠れているかも知れないもの。本書を通してその一端に触れることで、これまでとは見える景色が変わりました。
著者 東田直樹さんについて
東田直樹さんは重度の自閉症であり、会話が困難な方です。大人になられたご本人の様子はYoutube上で、お笑いコンビexitさんとの対談動画などで見るこができます。実際喋るのはあまりお得意ではないようで、彼の自閉症が嘘でないものであると確信することができます。
1992年千葉県のお生まれ。現在PCおよび文字盤ポインティングにより、コミュニケーションが可能だそうです。前述の動画では紙にキーボードの配列で文字を書いた文字盤を指さしながら声での会話をされていました。
ご本人の言葉を借りると、「文字盤ポインティングは、話そうとすると消えてしまう言葉を引き出すために考えたコミュニケーション方法で、僕は画用紙に書かれたキーボードと同じ配列のアルファベットを、ローマ字打ちで一文字一文字指しながら自分の思いを伝えています。」とのこと。思い浮かんだ言葉は口から出る前に散らばってしまうため、指さしで繋ぎ留めながら次の言葉と繋げていくのだそうです。
原著「自閉症の僕が跳びはねる理由」
本書は東田さんが13歳の時に執筆されたもので、自閉症である本人が「なぜこんな行動をするのか」「その時心ではどう感じているのか」「自閉症の人から世界はどう見えているのか」などを率直に語っておられます。
その内容もさることながら、世間一般の中学生でもそうは書けないほど理路整然とした美しい文章を綴られている事が銀猫にとっては一番の衝撃でした。書籍化するにあたりある程度以上の手直しはあったのでしょうが、子供の書いた文章の書籍化としては群を抜いて美しい書きぶりだと感じました。
それはつまり、当時の東田さんの内面にその文を書くだけの言葉と精神の蓄えがあった証明です。重度の自閉症であっても、内面にこれだけの世界が広がっているのだと知ることができたのがこの本に出会えた一番の収穫だと言っても良いかも知れません。
以降に、特に印象に残った内容を挙げさせていただきたいと思います。
外に表現されているのは本心ではない
頭に浮かんで伝えたいことと、口をついて出る言葉が違ってしまうと彼は言います。頭ではAだと思っていても、口はBだと喋っている。結果、周囲には誤解されて伝わってしまう。
これについては自閉症の全員が当てはまるわけではないと思います。というのも、息子がジェスチャーやクレーン現象で伝えてくる内容は少なくとも本人の希望に沿った物だからです。自閉症の程度によるのか、「スペクトラム」と呼ばれる個々人の特性差ゆえなのか。それは知る由もありませんが……
ただ、このことを頭の隅に置いておく事は重要だと感じます。わが子の言動が支離滅裂だと感じる日が来たとき、実は本心が口に出せていないのでは。と察する事で親自身がパニックに陥る事を防ぐことができるだろうと思うのです。
定型発達とは異なる自閉症児の「記憶」
通常、我々は自身の記憶を時間を軸にした「線」で認識しています。東田さんの中での記憶はこの「線」の認識がされておらず、バラバラの「点」で認識されているそうです。
過去の記憶も今の記憶も、同列の点。日付の認識はあるそうですが、日付順にファイリングされた記憶を手繰る我々と異なり、様々な色の点がずらりと並んだ中から該当の記憶を探す作業は難易度の高いことだろうと思います。
また、何か行動をする際には「過去にこのシチュエーションで成功した事例」を記憶から探す事から始めなければならないそうで、状況を理解する→正解の行動を記憶から探す→記憶をなぞって行動するという順序を踏むというのが印象的でした。恐らく一般の人も無意識にはこういった経路を辿っているのでしょうが、先の記憶の探しづらさが重なった時には果たしてどうか。やはり特筆に値するハードルとなるのではないでしょうか。
記憶が新旧で同じ鮮やかさで保たれているという事は一見して良いことに思えますが、裏を返せば失敗の記憶や嫌な記憶もいつまでも鮮明であるということ。何かの拍子に辛い記憶が当時のままの強烈さでフラッシュバックし、パニックに繋がることもあるようです。
また、突然笑いだすことについてもこの特徴が影響しているようです。ご本人が「思い出し笑いのとても強烈なもの」とおっしゃる様に、これも古い記憶が鮮明な影響なのだろうと思います。
僕が跳びはねる理由
東田さんにとって跳びはねたり、回転したり、そいうった行動は楽しさ以上に「自分の存在を確かにする」という意味があるのだそうです。
そう言われて意識してみれば、これは銀猫にも想像できる部分があります。漫然と意識が散っている状態で、例えばその場で軽くジャンプを繰り返す。足に感じる反動が、上下する視界が同じ周期で繰り返されて感覚が集中する。散らばっていた意識が集中して世界が「確か」になる。そういう事なのではないかと推察します。
著書の中で、東田さんは「自分の体はいつだって思い通りにならない。壊れたロボットを内側から操縦しているようなもの。」とも仰っていました。ままならない体に悩んでいるのは、周囲以上に中にいる本人。息子もそうなのだろうかと思うたび、大泣きする息子の内心を想像するようになりました。
映画「僕が跳びはねる理由」
東田さんの原著を翻訳して2013年に出版された「The Reason I Jump」を基にしたドキュメンタリー映画で、2020年に制作されました。
東田さんに直接触れることはほとんどなく、数組の自閉症の方とその家族のエピソードが語られてゆきます。原著の内容だけでなくそれぞれのリアルが映されており、そういった意味でも大変貴重な作品です。
作中では文字盤を使った筆談も実際に登場します。息子がこのまま言葉を喋れなかった場合はこの筆談を活用できるのでは……と検討している状況です。
今回は書籍・映画の両方を紹介しましたが、銀猫個人としては書籍の方が視点が1人で読みやすく、理解もしやすかったと感じました。
それぞれの深い意義を持った作品達ですので、お時間の許す限り両方に触れてみて欲しいと思います。
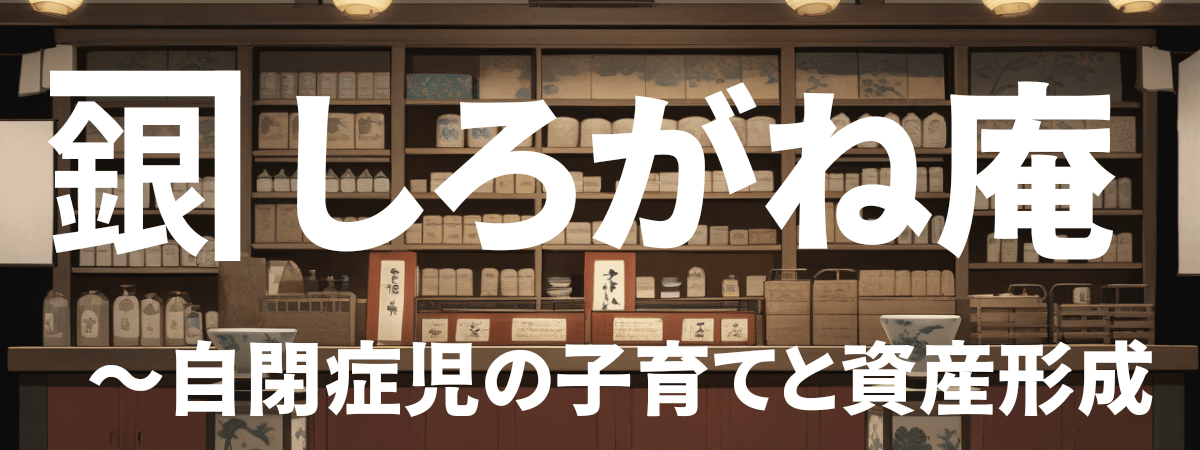
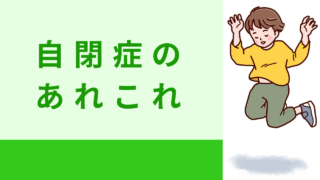


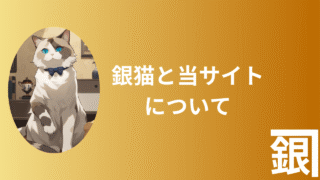
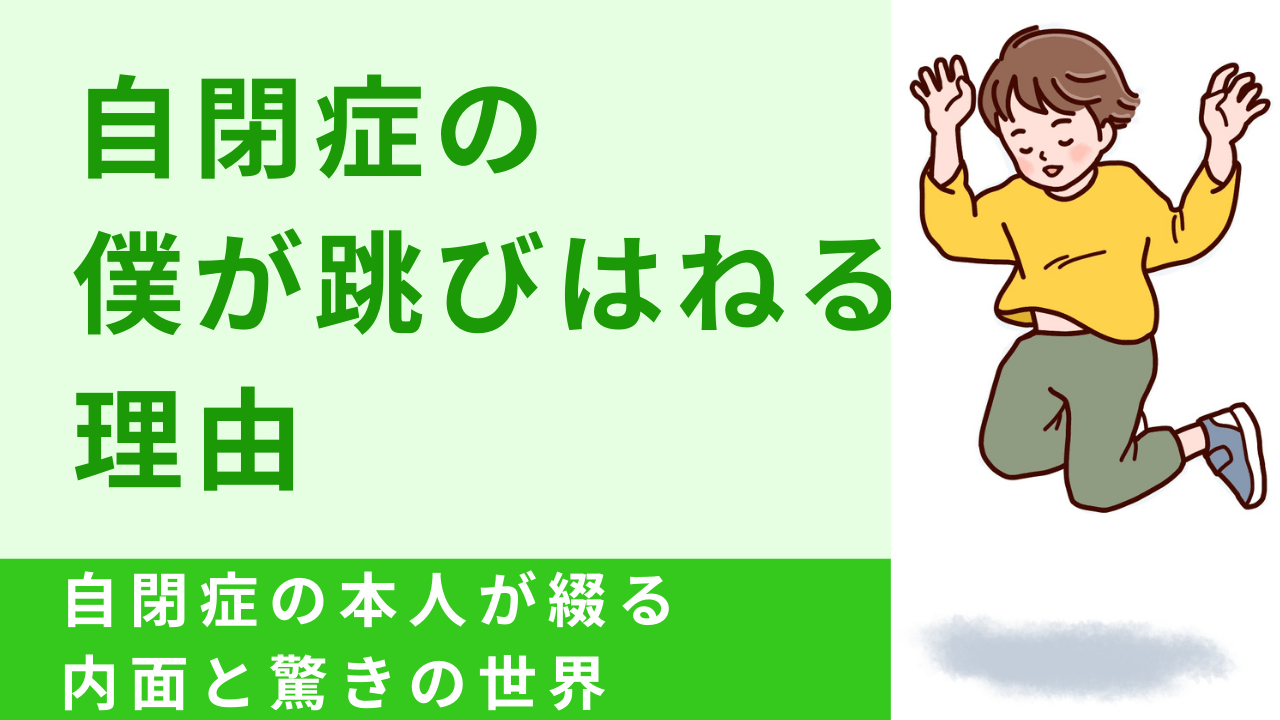
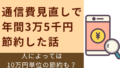
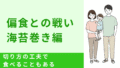
コメント