先日、市内の発達障害サポート団体様が主催された「発達個性を生かす特化能力」という講演会を聴講してきました。
講師は「文字職人」杉浦誠司氏、自立支援学校「耕せにっぽん」代表 東野昭彦氏、伊勢クロフネファーム代表取締役 案浦豊土氏のお三方。杉浦氏はASD(自閉症)東野氏はADHD(多動症)の特徴をそれぞれ持っておられるそうです。
それぞれのお話が非常に学びの多い講演で、とても刺激を受けました。それぞれのお話の要点をまとめるとおおむね以下のようになります。
- 固定観念を外す事で思いもよらない視点で物事を見ることができ、それが突破口となって居場所づくりや生きがいの鍵になることもある。縛られない視点を持つことが大切。(杉浦氏)
- 他者と比較し、勝ちたいと思う心は時に重荷となって引きこもりや家庭内暴力などの引き金となる事も多い。「人に勝ちたい心」よりも「人の役に立ちたい心」を育てる事が非常に大切。(東野氏)
- 発達障害を「得意なことに特化した個性・能力」と捉えることで活躍の場を見出す。自閉・多動の特徴は障害として現れていないだけで全ての人が備えている特徴であり、その割合がその人の性格や個性を形作っている。個性を理解して適所に配置することで、障害の有無に関わらず活き活きと活躍することができる環境を作ることができる。(案浦氏)
文字職人 杉浦誠司氏の講演
……実をいうとほかの用事とバッティングしてしまい、杉浦氏の講演は途中からの参加でした。そのためプロフィールの部分は聞くことができなかったのですが……
非常に厳格な家庭に育った杉浦氏は自信の持てないまま大人になり、「何者かになるため」就職してガムシャラに働いたそうです。その後会社で結果を出され、独立・挫折……。失意の中、文字を書いて仕事にしたいと思い立った杉浦氏は奥様の理解と励ましを得て活動を続け、今ではプロ野球球団にも作品を提供するほどの実力を身に着けてご活躍中です。
聴講できた範囲では、固定観念を外して考えることの大切さを一貫して説かれていたように思います。例の一つとして「弱虫」のお話を紹介したいと思います。
※これはあくまで固定観念を外して物事を別角度から捉える例えのお話ですのでご注意下さい。
「弱虫」の対義語は何でしょう?「強虫」……とは言いませんよね。
では、なぜ強虫という言葉がないのか?
答えは「強」の字の中に既に虫が入っているから。
杉浦氏はこの虫の字を虫の居所と表現しました。
弱い人は虫の居所が自分の外。他者の影響で動揺しやすく、他責思考になりがちなため気持ちが安定せずに生きづらい。一方強い人は虫の居所が自分の中。自責思考で行動し、他者の影響を受けにくいぶん強靭です。
その発想は無かった、上手いことを言うなと感心しました。あくまでこれは例え話ですが、固定観念の枠を外すことで多角的に物事を捉え、気付かなかった良さを見つけ出すことができるという示唆であると思います。
特性を持った子供たちの良さを見つける方策の一つとして、このような視点はとても勉強になりました。
耕せにっぽん代表 東野昭彦氏の講演
元々はお笑い芸人からいくつかの経歴を経て、自立支援学校「耕せにっぽん」の代表を努めていらっしゃる東野氏。お話の要点をまとめると
- 耕せにっぽんで関わった傾向から、引きこもりになってしまう子供は真面目な子が多く、「比較の価値観、勝敗付けの価値観」ばかりに潰されてしまった子が非常に多かった。
- 問題を抱えた相手への対し方。寄り添って対応する方法もあるがこれは問題に対してがっちり四つに組むやり方。問題を問題と扱わないことで意識の負担を軽くする方法もある。(つらい意識や被害者としての意識が薄れて心理負担が減る)
- 「誰かに勝つ」視点は悪ではないが「誰かの役に立つ」視点の教育が欠けがち。両面必要な考え方。
大きくこの様なお話でした。
特に比較の価値観から脱却する事については、銀猫自身とても納得できるお話です。
私の息子は知的障害を持つ自閉症です。どこまで伸びてくれるかわかりません。言葉が話せるようになるかも、わかりません。
銀猫自身を含め、多くの人が身を置く競争社会では勝ち残ることは難しいかも知れません。
でも、だから何だというのでしょう。敢えて強調します。だからどうした。という話なのです。
競争に負ければ幸せになれない、そんな事はありません。
本人が信頼できる環境に居て、やりがいを持って社会と関わることができる。これが一番大切なことだと銀猫は考えています。
当然、沢山の努力は必要です。「勝つための努力」ではなく、「誰かの役に立つために」出来ることを育てる努力が必要だと思うのです。
東野氏は学校教育においても比較の価値観から脱却し、人を喜ばせる・人の役に立つ事が大切なのだと教えて欲しいとお話しされていました。

少し横道に逸れますが、銀猫が資産形成カテゴリーで紹介しているリベ大の両学長も「仕事の本質は他者への価値提供。人の役に立つからお金がもらえる。」と仰っています。切り口は違いますが、根底の考え方は同じですね。
伊勢クロフネファーム 案浦豊土氏の講演
案浦氏の公演は、運営されているカフェでのより具体的な事例と、障害のあるなしに関わらず人間には必ず存在する自閉・多動の性質についてのお話でした。
どれも大変面白い内容だったのですが、概要としては
- 身体障害、知的障害など色々なスタッフが所属しているが、スタッフの「できること」を見つけて活かし、「できないこと」は他が補う仕組みを構築している。
- 特に障害が重い方々は人から優しくされる経験はあっても、「信頼して任される」経験をしていない場合がある。任された責任を果たすことは自己肯定感に繋がり、本人の喜びになる。
- チェックシートによる自閉、多動傾向の診断と、傾向別の活躍シーンについて。
というものでした。どれも濃いお話だったのですが…
例えば、あるスタッフは体の都合で握力に制限があり、お皿を10枚まで持つことはできません。ホールスタッフとしては作業に時間がかかってしまいますが、握力を使わない電話応対はできる。そこで電話での予約対応をしてみたところバッチリと相性がはまり、仕事を任せることができました。
ある知的障害のスタッフはどんなに頑張ってもアナログ時計を読むことが出来ず、1000円から上の計算ができず、漢字を漢字として覚えることができません。でも、人の顔を覚えることに凄い記憶力を発揮し、店外でも一度会っただけのお客様を見つけ、会釈ができる。その事を喜んだお客様が固定ファンとなり、カフェの看板娘として人気になりました。
まさに、適材適所という言葉の好例ですね。
自閉・多動の性質のお話については、「どちらの性質も全人類の中に備わっており、割合とレベルが異なるだけ。それが一定の水準を超えると『障害』とされるが、本来は個性の範疇の性質である。というものです。
チェックシートで点数を付けていくのですが、それぞれの中でもリーダー型・補佐型に分かれています。

ちなみに銀猫は自閉傾向強め、リーダーも補佐もどっちも行けるタイプでした。何となく納得……
自閉傾向の強い人は腰を据える作業に向き、多動傾向の強い人は営業や広告塔などコミュニケーションとフットワークを要求される作業に向く。マネジメントの界隈ではよく言われるお話だそうです。
知的障害者のブレイクスルー
案浦氏の講演中、氏が福祉担当者から「知的障害の子は伸びしろがない。」と言われたというお話しがありました。
心情的に納得できなかった銀猫は、質問コーナーで疑問をぶつけました。

私の息子は知的障害を伴う自閉症です。先程の講演中に「知的障害は伸びしろがない」と言われたお話がありましたが、クロフネファーム様では知的障害の方が成長できたブレイクスルーのような経験はおありでしょうか?

実はあります。先程の看板娘さんの事例です。
彼女は在職中どう頑張ってもアナログ時計が読めず、1000以上を数えることができませんでしたが、唯一、あるお客様の名前を漢字で書けるようになったのだとか。
ある常連の老夫婦が、看板娘さんの熱烈なファンだったそうです。他のスタッフがその方の予約を取っているのを見て、看板娘さんは言いました。

案浦さん、○○さんの名前漢字で書いたら、○○さん喜んでくれますか?

それはもちろん、喜ぶと思いますよ!

それなら、頑張ってみます!
そう一念発起した彼女は練習に励み、遂にはその方の名前を漢字で書けるようになったそうです。その方の名前だけで相変わらず他の漢字は書けないのですが、常連さんを喜ばせたいという気持ちがスイッチとなって障害の壁を1つ破ったのです。
漢字で書かれた予約票を常連さんは感激され、今まで受け取ってきた予約票を全て綴ったファイル(!)を見せながら「最初は平仮名だったのが、ずっと頑張って今こんなに成長したのよ!」と熱弁されていたそうです。
ちなみに、形と画数が似ている案浦氏の名前はいくらお願いしても書けなかったそう。案浦氏が常連さんほどは喜ばないことを見抜かれていたんだとか。
全体を通してとても学びの多い講演だったと思います。
今後も勉強を続けながら、息子のより良い人生を模索していきたいと想いを新たにできる切っ掛けとなりました。
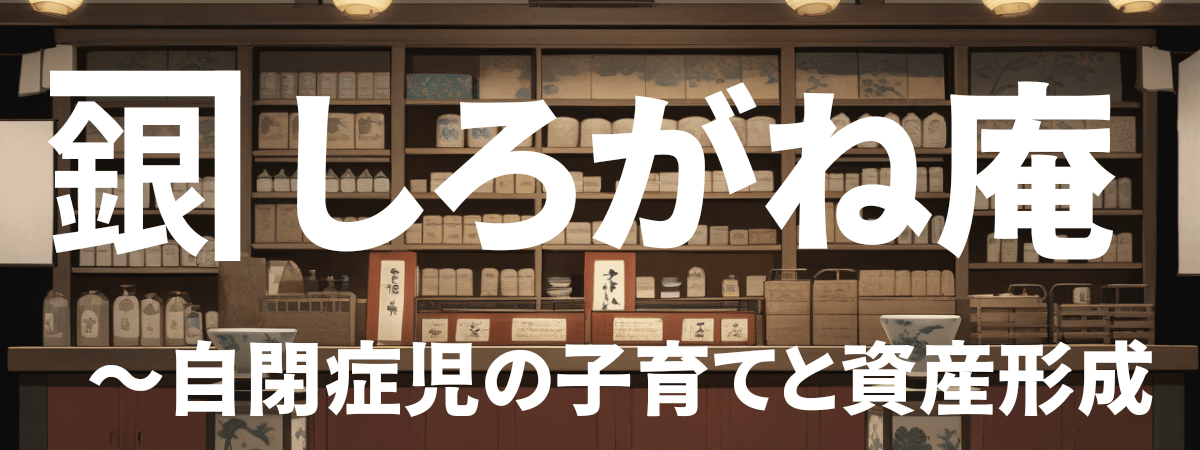
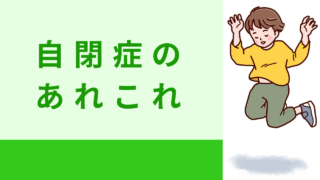


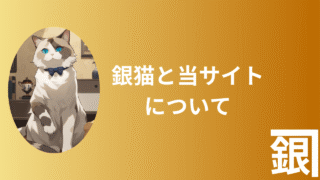
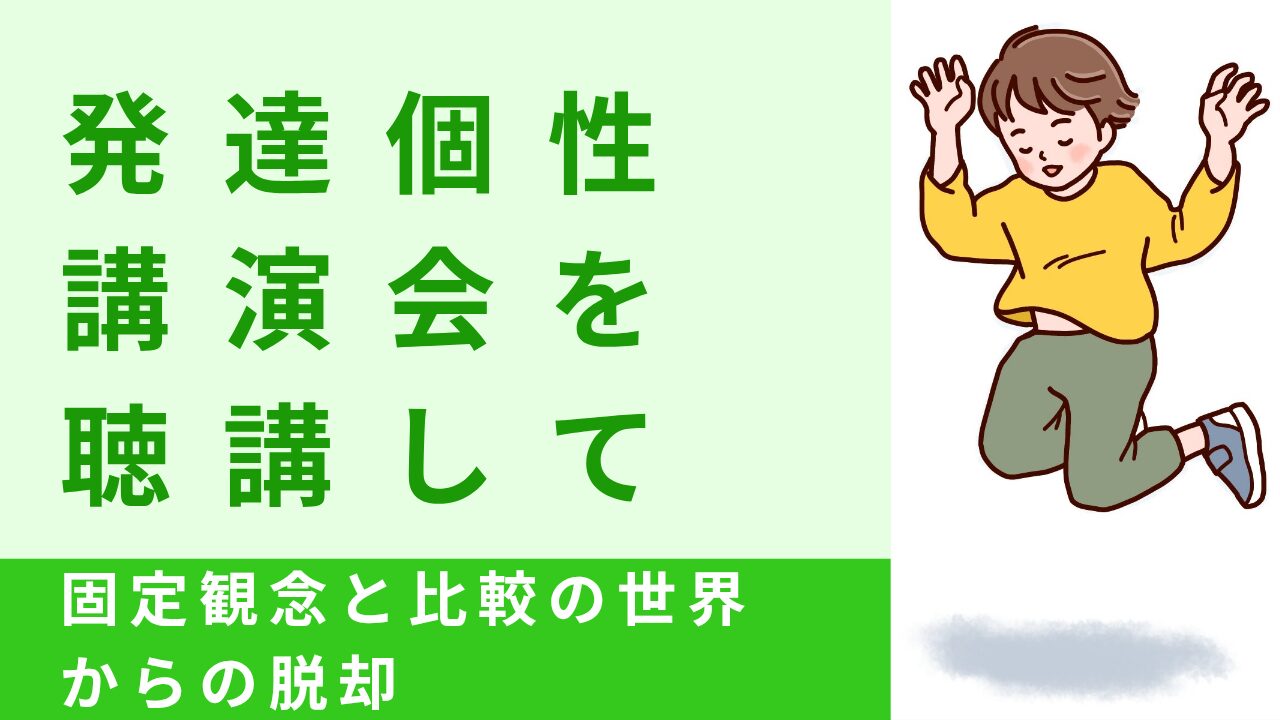
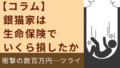
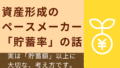
コメント